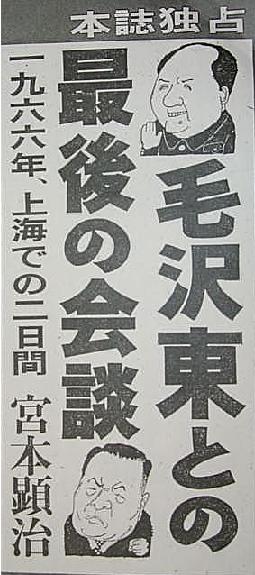
「こんなコミュニケは何の役にも立たない」――毛沢東主席のこのひと声で、いわば中国共産党と日本共産党の、”断絶”が始まった。十一年前のことである。いったい毛主席と、日共代表団長宮本顕治氏(当時党書記長)との間に、どんな激論がかわされ、何が毛主席の逆鱗にふれたのか。当事者の宮本氏が、いまその真相を明らかにする。
| ここで紹介する文献は、1977年、昭和52年に、日本共産党の宮本顕治氏が週刊朝日(昭和52年6月24日号)に発表した手記「毛沢東との最後の会談」です。宮本氏は、日中両共産党の断絶の直接のきっかけになった1966年3月の会談の経過について、氏の目からみた事実を比較的抑えた調子で淡々と記述しています。この手記からは、当時の宮本氏および彼の同志たちである日本共産党の氏と同世代の指導者たちの眼に、国際共産主義運動やベトナム戦争などの世界情勢、国内の共産主義運動、民主主義運動などがどのように写っていたのかを窺い知ることができると思います。宮本氏の手記に、「週刊朝日編集部」の前書きと注が付されています。 |
| 2000年8月18日 猛獣文士 |
| 毛沢東との最後の会談 |
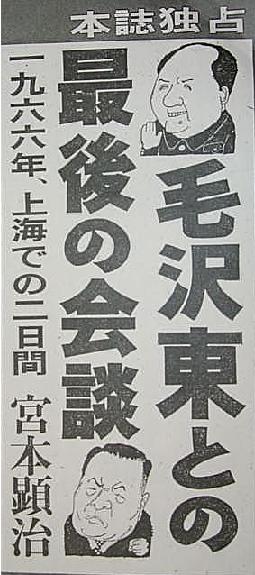
|
|
| 一九六六年、上海での二日間 宮本顕治 | ||
| 週刊朝日(昭和52年6月24日号)より | ||
|
「こんなコミュニケは何の役にも立たない」――毛沢東主席のこのひと声で、いわば中国共産党と日本共産党の、”断絶”が始まった。十一年前のことである。いったい毛主席と、日共代表団長宮本顕治氏(当時党書記長)との間に、どんな激論がかわされ、何が毛主席の逆鱗にふれたのか。当事者の宮本氏が、いまその真相を明らかにする。 |
|
北爆開始の翌年の一九六六年二月、日本共産党中央委員会は、ベトナム侵略反対の国際統一戦線の結成を願って、ベトナム、中国、朝鮮の三カ国の共産党、労働党と会談するために、大型の代表団を送ることになった。代表団は二月九日、福岡の若松港から、中国の貨物船「紅旗」号で上海にむかった。
一行は、団長が当時書記長だった私で、副団長長岡正芳幹部会員、団員は蔵原惟人、米原昶両幹部会員、不破哲三、上田耕一郎、工藤晃各中央委員候補だった。随員は小島優、立木洋の両名。なお、北京に駐在していた砂間一良書記局員も中国到着後、団員にくわわった。

|
| 毛主席(右側手前2人目)と会談する宮本顕治氏(ただし、1959年2月、鄭州でのもの。1966年3月の毛・宮本会談の写真は中国側から日共側に提供されなかった) |
上海では、政治局員の彭真、同候補の康生、中央委員で当時の中国共産党国際連絡部長劉寧一らが参加した歓迎宴がおこなわれ、また、これらの人びととの会談をおこなった。この会談は、後に予定されていた北京での本格的会談への予備的なものに過ぎなかった。
二月十七日にハノイに入り、ホー・チ・ミン主席、レ・ズアン第一書記、チョン・チン政治局員らの歓迎宴、レ・ズアンを団長とする代表団との会談をおこない、十日間の滞在ののち、共同コミュニケに調印し、二月二十八日には北京に到着した。
その日、人民大会堂でおこなわれた歓迎宴には、中国側から党副主席の劉少奇、周恩来、総書記鄧小平、政治局員李富春、李先念、同候補陸定一、康生、葉剣英、劉暁、劉寧一、蕭華、謝富治等々らが列席した。会談は三月三日から始まったが、中国側の顔ぶれは、劉少奇、鄧小平、彭真、康生、劉寧一、廖承志、呉冷西、張香山、趙安博であった。
北京には一週間余滞在し、四回にわたって会談した。会談では双方の主張に共通点もあったが、不一致点も大きかった。簡単にいえば、「アメリカのベトナム侵略に反対する国際統一戦線」か、「反米反ソの統一戦線」かの違いだった。双方が意見をつくしたが、どちらからも共同声明やコミュニケを出そうという発意はなされず、私たちは次の訪問地の朝鮮へむかった。
三月十一日に平壌に着き、二十一日に共同声明を発表して平壌を発った。この日、北京に着いたが、私たちは北京はただ通過するだけで、そのまま帰国する予定であった。
ところが北京空港で私たちを迎えた中国側から、日本共産党代表団歓迎の大集会を開きたい、共同コミュニケを発表したい、との申し出がなされた。思いもかけないことだったが、協議のうえ、ことわる理由もないので応じることにした。
二十六日北京で開かれた代表団歓迎大集会には、周恩来、朱徳(副主席)、彭真、康生、廖承志、林楓、劉暁、劉寧一ら多数が出席し、私と彭真がそれぞれ党を代表して演説した。私の演説全文は「人民日報」でも報道された。
共同コミュニケについては、すでに双方の不一致点は明りょうだったし、中国側がそのうえであえてコミュニケを出そうと申し入れてきた以上、不一致点は保留し、一致点でまとめるという良識を前提にするだろうと、私たちは考えた。このときには、朝鮮訪問前の北京での両党会談に参加した劉少奇はパキスタンに旅立っており、鄧小平は地方出張ということで、先方の会談の責任者は周恩来だった。
共同コミュニケを起草する小委員会は、当方は岡、米原、不破、上田、先方は劉寧一、呉冷西、張香山、趙安博のそう方四人ずつで設けられた。初めに日本側が草案を示し、それに中国側が対案を出した。
中国側は、ソ連共産党を名指しで批判する案を出したが、ソ連共産党指導部に批判をもっている点では双方共通しているものの、ソ連の権力の性格の評価、国際共産主義運動と国際統一行動での位置づけなどでは、双方に見解の違いがあった。また、私たちは共同コミュニケで第三党を批判するというやり方はとらないという態度だった。小委員会は五日間六回の会議で討議をつくし、結局、一致点を書くということで、ソ連への名指しの批判はコミュニケにはもられなかった。出来上がった共同コミュニケは、アメリカのベトナム侵略を激しく糾弾し、それとたたかう国際統一戦線の呼びかけを重視し、アメリカ帝国主義を美化する現代修正主義とたたかう、といった点を中心にし、さらに国際民主運動の分野での活動の強化、アジア諸国の労働者階級と人民の連帯、日中両共産党の友好と連帯などをうたった約三千字のものとなった。
周恩来を団長とする代表団との最終会談で共同コミュニケを確認し、翌日は上海にむかうという三月二十七日の夜、人民大会堂で私たちの歓送宴がひらかれた。周恩来、譚震林、康生、林楓、廖承志、劉寧一らが列席し、各界人士三百人ほどが参加した。北京在住の日本人も参加していた。この席で周恩来は「日中共同コミュニケの発表はアメリカ帝国主義と現代修正主義に大きな打撃を与えるだろう」といい、私も「このコミュニケは敵に対して打撃を与え、見方には勇気を与えるだろう」とのべ、ともにその成立を祝って乾杯した。
もちろん、このとき私たちは、これで中国側との正式会談は全部終わったものと考え、あとは共同コミュニケをいつ発表するかを、中国側ととり決めるだけと考えていた。朝鮮訪問以後の私たちの中国での日程を、中国側は、今回の中国訪問の「第三段階」と呼んでいたが、上海にいる毛沢東との会見も、共同コミュニケに書き込まれていた。したがって、共同コミュニケの発表は、上海での毛沢東との会見のあと、できるだけ早くと考えていた。
私たちの会談の経過や共同コミュニケの内容は、当然、党主席である毛沢東に報告され、その指示と了解のもとにすすめられたであろうということを私たちは一点も疑わなかった。上海で予定されている毛沢東との会見は、いわば表敬訪問的なものであると、私たちは考えていた。
三月二十八日、私たちは朝七時四十分北京発の特別機で上海に向かった。同行したのは康生、趙毅敏、趙安博だった。趙毅敏は中央委員候補、党国際連絡部副部長で、北京での両党会談には出席していない。
上海の空港には午前九時半に着いた。康生、趙毅敏らがまず毛沢東のところへ行って、事前の報告や打ち合わせをするというので、私たちは空港で小一時間待機した。毛沢東邸へ行ったのは十時二十五分くらいだった。広大な邸宅で、門を入ってしばらく自動車で走ってから、やっと玄関に着いた。毛沢東との会見には、先方も少人数らしいので、幹部会員と書記局員が参加することとし、私と岡、蔵原、米原、砂間の五人が会見の部屋に入った。広い部屋で扇形に安楽椅子が並べてあり、私たちはその一翼にすわった。
まだ毛沢東は見えず、趙毅敏、趙安博、魏文伯らがいた。まず趙毅敏が口をきった。
「コミュニケについて、毛主席に若干の意見がある。かなりよくできているが、これでは主題がはっきりしない。痛くもかゆくもないコミュニケだ。これではなんのために出すのかわからない」。そして彼は、毛沢東の修正点を口頭でのべた。
私はこれには驚いた。中国共産党の主席である毛沢東が、北京での両党会談で正式に確認されたコミュニケに、今になってこのような意見を出すのは一体どういうことか。毛沢東は、北京での両党会談に責任を持たないという立場なのか。中国共産党は一体どうなっているのか。私は、この唐突な思いもかけないできごとから、きわめて異常な、重大な事態を感じた。
毛沢東の修正案というのは、実際にはコミュニケの基調を別のものに変える提案であり、また北京での会談では出なかった新しい問題も含まれていた。
修正案は第一に、原文がアメリカ帝国主義に反対する国際統一戦線であるのにたいし、「全世界の革命的人民との団結」という革命路線の統一戦線を強調し、第二に、原文の現代修正主義という言葉に「ソ連共産党指導グループを中心にした」という規定をくわえ、また第三は、両党内の教条主義とセクト主義反対、特に「現代修正主義の思潮に断固反対」という、党内闘争の課題を提起したものだった。
第一、第二の問題は、結局「革命党」と認められるものの範囲内での共同闘争をして、ソ連を国際統一行動から名指しで排斥するという、北京の会談での中国側の主張の復活提案であった。第三の問題は、それぞれの党の党内闘争の性格まで規定するもので、北京の会談でも出なかった論点であった。
当時、日本共産党はソ連共産党と公開論争を続けていた。それは、ソ連共産党指導部のわが党への公然とした一連の攻撃、志賀義雄一派と「日本のこえ」への公然たる支持、プラウダ、モスクワ放送などでのそれらの反復などに端を発したものである。フルシチョフらの一連の方針に顕著に現れていた、ケネディを頭とするアメリカ帝国主義の美化論とその押しつけにたいし、私たちは率直な反批判をおこなっていた。
中国共産党とソ連共産党のあいだでも、当時すでに数年に及ぶ論争がおこなわれていた。しかし、日本共産党と中国共産党の立場には、以前からかなりの相違があった。中国共産党指導部の立場は、国際共産主義運動の分裂不可避論であり、事実、その立場からいわゆる「左派」の党を各国にどんどん組織していた。もっとも、毛沢東は、広範な反米統一戦線の重要性については、一九六五年五月までは、日本人民、パナマ、コンゴ人民などの闘争についての声明、談話でたびたび強調していた。
日本共産党は、ソ連指導部の根強い大国主義的干渉と対米追随路線をきびしく批判しながらも、同党指導部が一定の時期から、正確には一九六五年三月以後、アメリカ帝国主義のベトナム侵略に反対する共同行動を呼びかけていることに、注目していた。そして、ソ連共産党がベトナム人民の闘争に、物質的にも具体的な援助をおこなっている以上、アメリカ帝国主義に反対する国際統一戦線へのソ連の参加を拒むべきではないという立場だった。そして、その共同行動のなかで、正当なことは肯定し、正しくないことは肯定しないという明確な態度、いわゆる革命的ニ面政策をとることによって、事態は発展するというのが、私たちの見地だった。

|
| 北京での両党会談参加者の記念撮影(1966年3月3日)。前列右から康生、米原昶、彭真、岡正芳、劉少奇、宮本顕治、鄧小平、蔵原惟人、砂間一良の各氏 |
これにたいして、北京階段で中国側が強調したのは、ソ連と統一行動をとれば、修正主義と革命的立場の境界線がわからなくなり、「左派」の党を混乱させる、ソ連は不介入の日和見主義政策から、アメリカに対する妥協的解決をベトナムに押しつけるための介入政策をとろうとしているに過ぎない、という主張だった。
私たちは、統一戦線問題の国際的経験について、レーニンの一九ニ一年の第二インターナショナル、第二半インターナショナルへの統一行動の呼びかけその他を、全面的に研究し、革命勢力でないから統一行動の相手にしないという立場はとるべきではないという結論に、しっかりと立っていた。三カ国訪問前に発表した論文「アメリカ帝国主義に反対する国際統一行動と統一戦線を強化するために」(「赤旗」一九六六年二月四日)はこの立場の詳細な展開であった。
したがって、アメリカ帝国主義に反対する国際統一戦線の強化の呼びかけを、反米反ソの統一戦線の呼びかけに変える、といった提案に、私たちがいまさら同意する余地などまったくありえなかった。
私は、趙毅敏にたいし「このコミュニケは、もともと両党が完全に合意に達したうえでつくられたものではなく、意見の不一致があるなかでつくられたものだ。作成にあたっては両党から小委員を出し、一致点にもとづいて書く、不一致点にはふれない、できるだけ簡略にする、という三つの点を互いに確認し合ってつくった」と話し始めた。
このとき、毛沢東が康生とともに入ってきた。
私は毛沢東に会うのは、これが三度目だった。最初が一九五九年二月鄭州で、二度目が一九六四年秋杭州でだった。第一回目のとき、毛沢東から思いもかけず、一九五〇年の日本共産党の分裂時代にとった、中国共産党の態度が「誤っていた」ということばを聞き、私は毛沢東は大きな人物だという感じをいだいていた。(<(週刊朝日の)編集部注>参照)また、その中国革命についての理論と実践は画期的なものであると、長いあいだ評価していた。
さらに、一九六四年春、私が長い肺炎ののち、非常に衰弱して歩行も困難になり、中国の好意で海南島の暖かい気候のなかで療養していたとき、広東に来た毛沢東が、私に会いたいが療養中でもあるからやめたことを聞き、思いやりという点でも、私は毛沢東に好い印象をもっていた。
だから、この一九六六年の中国訪問にあたっては、それまでに中国側が発表していた一連の論文などから見て、合意はきわめて容易でないにしても、このような毛沢東なのだから、彼と冷静に話し合えば一致点も生まれるだろうという期待をもって、私たちは中国を訪れたのだった。
毛沢東は非常にきびしい表情で「孤立を恐れてはいけない。また戦争を恐れてはいけない。裏切者にたいしては融和的態度をとっては駄目だ。あなたたちは、志賀や右翼社会民主主義に対して融和的態度をとっているか」と切り出して、彼自身が過去に孤立した経験をのべ、レーニンも孤立を恐れなかったと力説した。そして「あなた方は孤立した経験があるか」と尋ねた。
私が「ある」と答えると、毛沢東はつづけて「アメリカはベトナム戦争を中国までエスカレートしようとしている。しかしわれわれは戦争を恐れない」、アメリカが中国を攻撃し、南から侵略を拡大したらソ連も北から攻め込んでくるだろうといい、莫大な犠牲も出るだろうが、犠牲を恐れてはならないとして、彼の長男は朝鮮戦争で戦死し、妻や弟、妹なども国民党に殺されたとの事例を挙げた。「しかし自分は生きている。二十二年間戦争をしてきたが、一発のたまもあたらなかった。これはマルクスに守られていたからだといえないだろうか」
毛沢東はさらに、アメリカの爆撃がベトナム人民を団結させ、日本の中国侵略が中国人民を団結させたということをのべて、戦争を恐れてはならないことをかさねて強調した。そして、「コミュニケにたいする私の修正案について意見はどうか」と聞いた。
私自身の考えは疑問の余地なくはっきりしていたが、団員間での意見はまだ交換する機会がなかったので、私は「あとで研究する」と答えた。
毛沢東は「私はあのコミュニケを読んでたいへん不愉快だった。これは主題がはっきりしない。現代修正主義とあるが、だれを批判しているのかわからない。中国共産党も日本共産党もソ連の修正主義を公然と批判しているのだから、はっきり名指しで書かなければ駄目だ。このコミュニケは妥協的だ。私はどうしてもいわなくてはならない。このコミュニケは勇気がなく、軟弱で、無力である」といった。私が「コミュニケは最初日本側で起草した」と発言すると康生は「われわれの提案もはいっている」とのべた。
毛沢東は「北京の連中もこれに同意したのだろう。軟弱だ。私の意見を押しつけるわけではないが、原文のままだと発表しないほうがよい」と緊張した表情で、ところどころ声を強めながらのべた。そして彼は「これで私の意見は終わる。今度はあなた方が私を攻撃する番だ」と話を結んだ。きわめて緊張した雰囲気が続いていた。
もう昼の十二時近くになっていた。
私は「毛沢東同志も率直に意見をのべた。われわれも率直に意見を交換するために来たのだ」と前置きして、自分たちの経験としてさまざまな誤った傾向とたたかって綱領を採択した経過にふれた。また、党が分裂したとき、スターリンがつくった五一年綱領のなかの極左冒険主義の方針で、党が大きな打撃をこうむった苦い経験から、自主独立の方針を確立して、今の綱領も自分たちの手で独自につくりあげたこと、この経験があったから一九六〇年の八十一カ国共産党・労働者党代表者会議の予備会議でも、はじめは少数だったが恐れず、独自の修正案を出して主張することができたこと、これは中国を含めて、どの党の指示のもとでやったことでもないこと、などをのべた。
また私は、ソ連共産党との論争の問題にふれて、公開論争が始まるまえに、原水禁大会で来日した趙安博が私に、「ソ連共産党との公開論争を早く始めないとバスに乗り遅れる」と「扇動」したが、わが党はこの「扇動」に乗らず、ソ連の党が公然とわが党を攻撃するまで、名指しの論争はやらなかったという点も指摘した。
さらに私は、わが党の第七回党大会で一九五〇年のわが党の分裂問題を総括するまえ、ソ連を訪問した志賀、蔵原にたいし、フルシチョフはこの総括をやめるようにいい、志賀、蔵原が帰途北京にたち寄ったさい、劉少奇もこの総括をやることに反対した。「当時ソ中は世界の二つの大きな党で相当権威をもっていた。しかしわれわれは孤立を恐れず、フルシチョフや劉少奇に追随した志賀の意見をしりぞけ、われわれの自主的な判断で五〇年問題の総括をおこなった」とのべた。
毛沢東が口をはさんで、「これは初めて知った」と、この劉少奇の件をかたわらの康生に聞いたが、康生は首をふって、知らない旨を示した。
私は話を続けた。
「ブカレスト会議でも、ここにいる米原同志が出席したが、フルシチョフの中国攻撃に賛成しなかった。これはだれに相談したことでもない。ソ連の第二十三回大会への欠席の問題も、どの党とも相談しないで独自に決めたことだ。中国との会談でもこれは話題にならなかった。このようにわれわれは孤立を恐れず、正しいと思ったことは、自主的な判断で勇気をもってやってきた」
「われわれは、ソ連共産党にたいしてきわめて原則的な態度をとっている。ソ連大使館のレセプションや革命記念日などの集会にも、彼らが志賀一派を参加させる限り断固として参加していない。その点ではわれわれはきわめて頑固派である」
「そういう頑固派はよい」と毛沢東が口をはさんだ。ソ連にたいする日本共産党の態度のくだりになると、毛沢東は少し表情をやわらげ、私たちのいくつかの態度について「あなたたちの方が進歩している」といって笑った。
私は、ベトナム問題の重要性を強調して、次のようにのべた。
「ベトナムの同志たちはよくたたかっているが、これにたいする国際的支援は必ずしもうまくいっていない。八十一カ国声明では社会主義の優位性ということをいっているが、いまベトナム問題では、その力を十分出し切っていない」
「中国が最悪の事態にそなえることはよいことだが、悪い可能性に備えるだけでなく、よい可能性を実現するために全力をあげる必要がある。中国に戦争が拡大した場合に備えることはもとより大事だが、ベトナム問題をベトナムで解決し、中国に拡大しないように努力することが大切だ。毛沢東同志もいったように、政治的に敵を包囲し、孤立させなければならない」
毛沢東が口をはさんで「もちろん政治的にも備えなければならない」とのべた。
「そのためにはアメリカに反対する一切の力を結集してゆく必要がある」と私は続けた。「あなた方は、ソ連の権力は資本主義になった、ファシストになったといっている。しかし、そういう規定をするには、いろいろ科学的な研究をする必要がある」
毛沢東も「研究する必要がある」といった。

|
| 1966年、毛主席は揚子江を泳ぎ、健在を印象づけた(UPIサン) |
わたしはさらに、国際民主運動のなかでの活動の問題、当時のインドネシアの事態の見方などについてものべた。
毛沢東は、コスイギンが中国に来て、公開論争をいつまで続けるのかと尋ねたのにたいし、一万年ぐらい続けるつもりだといったこと、かつて蔵原と会ったとき、共産主義は一国で可能かと聞かれ、できないと答えたこと、「資本主義の復活の問題は、たえずおきてくる問題で、たばこ二箱で買収されるものもある」こと、などを話した。
このとき、昼食の用意ができたとの知らせがあった。毛沢東が「食事にしてからまたやることにしては」と提案し、私たちも同意して食堂に入った。江青の姿は見かけなかった。
ときに、午後二時すぎだった。
会食には私たち代表団は全員が出席した。
会食時の毛沢東はかなりくつろいで、「中国の党は日本の党に干渉しすぎた」と、一九五〇年当時のことを、自分から反省的にもち出した。
私が「とても元気そうだ」というと、彼は「時どきせきがでてこまる」といい、話はたばこのことに移って、互いに冗談の応酬が続いた。たばこをやめると国家財政が破たんするといった冗談も出た。
毛沢東が「孔子は七十三歳で死んだ。私はいま七十二歳だが、今年七十三歳になる。そろそろ今年の終わりごろに、マルクスに会いに行けることになるかもしれない」というので、私は「このまえ会ったとき毛同志が、私の五カ年計画はマルクスのところに行くことだといったので、私はその五ヵ年計画には反対だといった。私はいまもその意見をかえていない」といった。蔵原は「この点でもよい可能性の方を追求してください」といった。
漢字制限の話も出て、毛沢東が「日本では漢字をどれぐらい使っているか」と問い、蔵原が「当用漢字で二千あまりある」と答えると、「まだそんなに使っているのか。漢字は早くやめて、ローマ字にしたほうがよい」といった。私は「それには反対だ。だが、この問題は研究課題として議題からはずそう」などといい、さらに話ははずんだ。
会食の最後に、毛沢東は「会談をどうする。私はもういうことはない」といった。私は「私の方はまだ残っている。そんなに多くはない」といった。毛沢東は「ではあすつづけよう」と答えた。終わりに一同ならんで写真におさまった。
私たちはその晩、代表団の会議をひらいて正式に毛沢東の修正提案について討議した。きわめて重大な原則的問題であるので、若干の字句の置きかえであいまいに処理することはできない問題であると、皆が発言した。会議の決裂による日中両党関係の将来は多難が予想されるが、私たちが原則的な態度をとらなければ、理論的にも重大な誤りをおかすことになるし、内外に重大な混迷を与えることになるという点で、皆の意見は詳しく論議するまでもなく一致していた。この点、代表団に「軟弱」なメンバーは一人もいなかった。
翌朝、毛沢東邸に着くと、趙毅敏がまずコミュニケについての意見をきいたので、「もしまとめるなら不一致点は保留し、一致点を簡潔に書いた原文のようなものとしてしかまとまらない」といって、私は問題点についての私たちの見解を詳細に説明した。そして、むしろ今日の会議は「コミュニケをまとめる問題に限定せずに、重要問題について話し合う良い機会だと思っている。お互いに自己の見解をおしつけることはできないが、話し合うよい機会だ」といった。
趙毅敏は、毛沢東に報告にいった。やがて毛沢東がはいってきた。そして、無表情に「まだ話すことがあるか」と聞いたので、私は「少しあるから話す」といって、前日の話の補足として語った。それは趙毅敏にもいったように、私たちの立場をいっそう明確にしておくことが、訪問の主旨にかなうからである。私はレーニンが第三インターナショナルをつくった時期と今日との比較、ハバナでおこなわれた第一回アジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯大会の評価などについてのべた。毛沢東は、私の話の半ばで「北京での会談の記録は見た」と、ポツリといった。おそらく昨晩見たのであろう。そして、もう私たちを修正案の線で同意させることは、まったくあきらめたように見えた。
私は、話が終わるまえに、「この会談をつうじて、論文を読むだけではわからないお互いの立場、論点やその根拠を知ることができた。一致しない点については、お互いにさらに研究し、こんごの実践の検証をえよう」とのべた。そして最後に、アジアの四党――日本、中国、朝鮮、ベトナムの、それぞれアメリカに領土を侵略されている国の党が共同しあうことが必要であると強調した。
「話すことは以上のとおりだ」と私は結んだ。毛沢東はいった。「私もこれ以上話すことはない。ただ一こと二ことある。あなた方の態度はソ連共産党指導部に歓迎されるだろう。これが一こと目。私たちは歓迎できない。これが二こと目。コミュニケは発表できない。あなたたちの方でコミュニケを出すことを要求しないのに、われわれが出そうといったのはまちがいだった」
「われわれは出すことに固執していない。われわれは、われわれの立場が、アメリカにもソ連指導部にも歓迎されないことを確信している。この点は意見が違うということだ」と私はいった。
毛沢東は「どちらの意見が正しいか、事実で証明しなければわからない。天は落ちてくることはない。今後機会があればひきつづき話し合える。これでうちきろう」とのべた。最後に先方は「この会談はなかったことにしよう」といった。そして、毛沢東は立ち上がって歩きながら「さあ、これで双方とも身が軽くなった。お互いに荷物をおろしたから」とつぶやいた。
毛沢東は二日目の会談ではわずかしか話さず、ニコリともしなかったが、それでも私たちが毛沢東邸を出るときには、玄関まで来て、私たちが自動車に乗るのを見送った。
私たちはその日、飛行機で広州に行った。広州の人たちは、私たちが毛沢東に会ったが共同コミュニケは出なかったということで、両党関係になにか起こっているということを感じて、ショックを受けたようだった。予定されていた大規模な宴会も、全部とりやめになった。
日本に帰ってから私たちは、先方が「なかったことにしよう」といったことも考慮して、約束したわけではなかったが、この会談については沈黙を守っていた。しかしその後、北京の「紅衛兵」の新聞が会談内容をゆがめて攻撃し、さらに岩村三千夫などが趙安博から聞いた話として、大変ゆがめた内容を伝えたので、私たちはその範囲内で必要な反撃をくわえた。
その後判明したことだが、私たちの会談の第一日、三月二十八日という日は、毛沢東があの「文化大革命」の“引き金”となったあの有名な指示――「私は地方にむほんを呼びかけ、中央に進攻することを呼びかける。各地は多くの孫悟空を輩出させ、天宮に攻めいるべきだ」という指示を出した日となっている。毛沢東が修正案のなかに、党内闘争にかんする規定をもち出した歴史的背景は、明白となった。(<(週刊朝日の)編集部注>参照)
それから十一年の歳月がたった。私たちが中国で会談した多くの人びとの身の上にも、有為転変があったようだ。周恩来、毛沢東も天界に去った。私はこの会談について、当事者としての判定を、改めてここに書きつけようとは思わない。ただその後の二つのできごとに、私の関心はそそがれた。
第一は、中国共産党指導部はその後、一九七一年六月にルーマニア共産党と、七一年十一月、七三年六月にベトナム労働党と、最近では一九七五年四月に朝鮮労働党と、それぞれ会談したが、どの共同コミュニケのなかにも反米反ソの主張は書き込まれなかったことである。
第二は、私たちの三カ国訪問の最大の主題であった、アメリカの侵略にたいするベトナム人民の解放闘争は、二年前にアメリカの全面撤退という完全な、世界史的な勝利をかちとったことである。私たちの重視した国際的な反帝統一戦線は、形の上では実現しなかったが、この間事実上世界の社会主義国、反帝勢力、すべての共産主義者の党が、それぞれベトナム人民を支援するという立場を表明した。そして、ベトナム人民の賢明で自主的な偉大なたたかいを土台に、アジアの歴史は大きく書きかえられた。
会談で毛沢東も、また機会があれば話し合えるといっていたように、両党間の意見の不一致は、両党関係断絶を少しも意味しなかった。しかし、その後遺憾ながら、日本共産党の中国駐在の中央委員や赤旗特派員らにくわえられた北京での集団暴行、日本共産党の路線への攻撃と干渉、中国追随の分派活動で党から除名された者への支持などが相つぎ、両党関係は断絶して久しい。
十年に及ぶこの断絶の期間は、短くはないが、しかし両党が生まれてからの長い友好の歳月から見れば、一期間に過ぎない。共産主義運動、社会主義国の誕生以来の歳月も、人間の寿命にくらべれば短くはないが、長い人類の歴史から見れば一瞬である。それぞれの国の人びとが、最善と思う道を探求しているが、歴史の検証はゆっくり待とう。
(週刊朝日 昭和52年6月24日号)
| (週刊朝日の)編集部注 |
<五〇年分裂と中国>
一九五〇年一月六日コミンフォルム機関紙は、「日本の情勢について」と題する論文のなかで、日本共産党の「占領下平和革命路線」は、「帝国主義占領者美化の理論」であり、「マルクス・レーニン主義とは縁もゆかりもない」と、日本共産党を激しく非難し、党内は大混乱となった。
徳田書記長を主流とする党政治局会議は志賀義男、宮本顕治ら「論評」受け入れ派の意見をしりぞけ、非難は日本の人民大衆として受け入れがたいとする「所感」を発表した。
しかし、やがて、「所感」の態度はまったく嘆かわしいと批評した「人民日報」社説の内容が伝えられ、徳田らは「論評」の受け入れを認めることになる。これを契機に、日本共産党は、分裂、大きな痛手を受けた。
<上海と文化大革命>
前年の六五年十一月、上海で姚文元の「『海瑞、官をやめる』を評す」が発表され、上海を中心に着々と文革の準備がすすめられていたが、この会談直後、毛主席や上海グループの動きがあわただしくなる。
一九六六年五月、毛沢東は半年ぶりに公式の場に姿を現し、上海でアルバニア党・政府代表団と会見、同年七月十六日には、五千人の人々の前で揚子江を泳いで見せた。「毛主席健在」をアピールしたのである。
このころ、毛沢東は、北京から遠ざけられて上海にいた、という説もあるが、宮本氏との会談での「毛語録」は、劉少奇・鄧小平勢力の強い北京、毛沢東を中心とした上海――といった文革直前の中国の雰囲気を伝えている。宮本氏らを前に演説した彭真は、その二ヵ月後に失脚した。